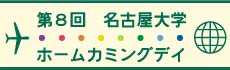テクノ・フェア名大2012
"未来を明日に近づける技術"
ミニ講演(展示内容概要説明) 11:40-16:50
| 開始時刻 | A会場(豊田講堂ホール) | B会場(豊田講堂3階) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 講師 | タイトル | 講師 | |||
| 11:40 | 部材軽量化・高精度化に挑戦する塑性加工技術 | 石川 孝司 | G C O E | グリーンイノベーションを指向する機能表面の創製と評価技術の最先端 (超低摩擦表面、低付着表面の創成) | 梅原 徳次 | |
| 12:00 | 次世代熱エネルギー輸送デバイス | 長野 方星 | これからのものづくりを支える切削加工技術を目指して | 社本 英二 | ||
| 12:20 | 休憩 | |||||
| 13:10 | 「太陽エネルギー社会」構築に向けた材料テクノロジーの創出 | 河本 邦仁 | 環境に優しい縮合触媒の開発: ボロン酸触媒を用いるアミド、エステル、カルボン酸無水物合成法 | 石原 一彰 | ||
| 13:30 | 省エネ技術の急先鋒・パワーエレクトロニクスのための次世代材料(SiC)開発 | 宇治原 徹 | エネルギー基盤材料としての耐熱金属材料 | 村田 純教 | ||
| 13:50 | G C O E | 硬くて、透明、長期持続可能な超はっ水膜・超親水膜 | 齋藤 永宏 | 金属およびセラミックス系複合材料・多孔質材料の構造制御による多機能化 | 小橋 眞 | |
| 14:10 | 沿岸防災のための高精度数値解析ツールの開発と応用例 | 水谷 法美 | 利用開始目前! 先端分析の新拠点 中部シンクロトロン光施設でわかること | 田渕 雅夫 | ||
| 14:30 | 休憩 | |||||
| 14:50 | 最 先 端 ・ 次 世 代 | 太陽電池への利用をめざした半導体ナノ結晶の化学合成と組織化 | 鳥本 司 | 新しい超短パルス光源を用いた3次元光断層計測技術 | 西澤 典彦 | |
| 15:10 | 植物由来のビニルモノマーからの新しいバイオベースポリマーの開発 | 上垣外 正己 | ナノ解析は名大超高圧電子顕微鏡グループへ | 春日部 進 | ||
| 15:30 | バクテリオナノファイバー蛋白質の機能を基盤とする界面微生物プロセスの構築 | 堀 克敏 | アンケートデータの見える化 | 吉川 大弘 | ||
| 15:50 | シリコンナノエレクトロニクスのための新材料薄膜と界面制御技術 | 中塚 理 | 癌の迅速診断デバイスの開発 | 笠間 敏博 | ||
| 16:10 | 高分子のらせん構造を活かした機能性材料の開発 | 飯田 拡基 | G C O E | 歯髄幹細胞由来成長因子を応用した新しい中枢神経治療 | 松原 弘記 井上 崇徳 |
|
| 16:30 | 見やすく疲れない3D立体映像をめざして | 宮尾 克 | ||||
A会場(豊田講堂地下1階)
(11:40~12:00) 部材軽量化・高精度化に挑戦する塑性加工技術
石川 孝司教授(工学研究科マテリアル理工学専攻)

部材の軽量化・高精度化技術は、自動車の安全性向上、燃費向上のためにますます重要となっています。塑性加工は、高速、高精度で低コストなプロセスであるため、自動車をはじめとして部材製造に欠かせない加工法であり、ものづくりの原点として日本の製造業を支えています。講演では、冷間鍛造による異材接合技術、傾斜特性付与鍛造技術、逐次鍛造技術、サーボプレスによる高精度成形技術について、CAEを駆使したシーズ研究を紹介します。
[キーワード]:塑性加工、鍛造、プレス、CAE
ホームページ
(12:00~12:20) 次世代熱エネルギー輸送デバイス
長野 方星准教授(工学研究科航空宇宙工学専攻)

低炭素化社会の実現には熱エネルギーの有効利用が不可欠であり、熱源からの熱を効率よく輸送できる技術が強く望まれております。本講演では電力を用いずに半永久的な熱輸送が可能なループヒートパイプ技術とその最新動向について総説し、高性能化と自律熱流動制御に向けた本研究室の取り組みを紹介します。
[キーワード]:エネルギー、環境、熱輸送
ホームページ
(13:10~13:30) 「太陽エネルギー社会」構築に向けた材料テクノロジーの創出
河本 邦仁教授(工学研究科附属材料バックキャストテクノロジー研究センター)

環境破壊・温暖化・気候変動・地球崩壊を回避して生命力溢れる地球を取り戻すためには、化石燃料依存型社会から一刻も早く脱皮し、原子力エネルギー依存から大きく方針転換して、無限に存在するクリーンな自然エネルギーを最大限活用する「太陽エネルギー社会」の実現を目指さねばなりません。MBTセンターは、「太陽エネルギー社会」を人類が目指す未来の理想社会と位置づけ、これを構築するために必要な「バックキャスト視点に基づく材料テクノロジー」を開拓します。具体的には、(1)光・熱・力学エネルギー変換・貯蔵・輸送技術に資する高機能材料、(2)低環境負荷型物質・材料製造プロセス、(3)高機能代替材料、等の研究開発を先導します。
[キーワード]:材料、バックキャストテクノロジー、太陽エネルギー
宇治原 徹教授(工学研究科マテリアル理工学専攻)

未来自動車「グリーンビークル」は低炭素化実現のため電池から供給される電気エネルギーを使用してモータを駆動する電動方式が主流となります。その中で電力変換を担うパワーデバイスは高耐久性と小型化が一段と高いレベルで要求され、従来のSi材料ではそれらの要求を満足できない状況です。本講演では次世代パワーデバイス材料として大きな期待が寄せられているSiC結晶材料について欠陥密度を飛躍的に低減可能な溶液成長法による開発技術を紹介します。
[キーワード]:半導体、パワーデバイス、パワーエレクトロニクス、結晶成長
ホームページ
(13:50~14:10) 硬くて、透明、長期持続可能な超はっ水膜・超親水膜
齋藤 永宏教授(グリーンモビリティ連携研究センター)

ガラス、金属、紙、繊維、セラミック、プラスチック等、様々な部材の自由形状表面に超はっ水・超親水加工する技術の開発をおこなっています。自動車用のフロントガラス、めっき被膜形成の前処理やインプラント等医療品用表面処理などに応用できると考えています。本講演では、私どもの研究室で取り組んでいる、自己組織化単分子膜やプラズマ技術を使う、超はっ水膜・超親水膜作製技術について紹介します。
[キーワード]:超はっ水、超親水、プラズマ、自己組織化単分子膜、めっき、医療、表面処理
(14:10~14:30) 沿岸防災のための高精度数値解析ツールの開発と応用例
水谷 法美教授(工学研究科社会基盤工学専攻)

津波・高潮・高波の作用により沿岸域では様々な災害が生じる可能性があります。このような沿岸域での防災・減災を講じる際には、各現象の予測技術の高度化のみならず、海岸施設及び避難施設の設計指針の確立が重要です。本ミニ講演では、当研究グループがこれまで開発してきた津波・高潮の氾濫モデルと伊勢湾への適用、数種類の三次元数値波動水槽の紹介とそれらを使った複雑な形状の構造物周辺の波浪変形解析例、遡上津波による陸上ビル群への作用やそれに伴う漂流物及び漂流衝突力の解析例、波・構造物・地盤の相互作用解析ツールによる構造物基礎の局所洗掘とそれに伴う構造物の不安定現象に関する数値例などを水理実験結果と比較しながらその有用性について紹介します。
[キーワード]:津波、高潮、沿岸防災、数値波動水槽
(14:50~15:10) 太陽電池への利用をめざした半導体ナノ結晶の化学合成と組織化
鳥本 司教授(工学研究科結晶材料工学専攻)

粒子サイズが10nm以下の半導体ナノ結晶は、単結晶などのより大きな材料とは異なった物理化学特性を示し、さらにサイズに依存して大きく変化します。このようなナノ結晶の変調可能な特性を利用して、新規光機能材料の開発が盛んに行われています。しかし、従来の半導体ナノ結晶は、Cd、 Pb、 Seなどの毒性の高い元素を含むためにその用途が厳しく制限されます。私たちは、広い応用が可能な材料であり、低毒性元素からなるCu2ZnSnS4およびZnS-AgInS2固溶体に着目し、そのナノ結晶の液相化学合成に成功しました。本講演では、これら新規ナノ結晶の作製法を概説し、得られたナノ結晶の光機能材料への応用、とくに量子ドット太陽電池への利用について述べます。
[キーワード]:半導体ナノ結晶、量子サイズ効果、フォトルミネッセンス、量子ドット太陽電池
ホームページ
(15:10~15:30) 植物由来のビニルモノマーからの新しいバイオベースポリマーの開発
上垣外 正己教授(工学研究科化学・生物工学専攻)

高分子化合物は、プラスチック・ゴム・繊維などとして現代社会を支える必要不可欠な化合物であり、その多くは石油資源から得られる有機化合物を重合することにより合成されていますが、近年、再生可能資源に基づく循環型社会の構築が重要視されてきています。本講演では、植物から得られるテルペン類やフェニルプロパノイド類などの多様な植物由来ビニル化合物を精密重合する方法を開発し、これら植物由来化合物の特有な骨格を活かしたポリマーを合成することで、機能や性能に優れた新規バイオベースポリマーへと導く、私たちの研究室の取り組みを紹介します。
(15:30~15:50) バクテリオナノファイバー蛋白質の機能を基盤とする界面微生物プロセスの構築
堀 克敏教授(工学研究科化学・生物工学専攻)

本研究課題は「最先端・次世代開発研究支援プログラム」(グリーン・イノベーション)に採択され、実施中のものです。昨年に続き本年も、テクノ・フェアにて本研究活動の内容や成果を社会・国民に対してわかりやすく説明します。以下は本研究の目的です。
「私は微生物が体(細胞)から出す接着性ナノ繊維を発見しました。それはユニークな構造をもつ蛋白質分子で、世界最強レベルの接着性を示しますが、その仕組みは不明です。このナノ繊維を使って、バイオエタノールやプラスチックの原料などをつくることができる微生物を、スポンジなどの担体表面にくっつけ、化学反応に使います。そのために、接着の仕組みと繊維の性質などを分子レベルで解明します。」
[キーワード]:付着、細菌、バイオテクノロジー
(15:50~16:10) シリコンナノエレクトロニクスのための新材料薄膜と界面制御技術
中塚 理准教授(工学研究科結晶材料工学専攻)

シリコン集積回路を中心とする半導体ナノテクノロジーの長年に渡る進化によって、現代の高度情報化社会は支えられています。集積回路のさらなる高速化、高機能化、省電力化を実現するために、私たちは、次世代の半導体材料として注目されるゲルマニウムや様々な絶縁膜、配線金属のための新材料の物性や材料同士の界面物性制御に関する研究開発を進めています。また、半導体結晶成長技術の応用によって、従来は存在しなかった新しいⅣ族系半導体材料を創成し、エレクトロニクス応用のみならず、新世代の高効率太陽電池や半導体回路上へ集積可能な発光・受光デバイス実現のための応用技術を開拓しています。
[キーワード]:半導体、ナノテクノロジー、集積回路、太陽電池、結晶成長、薄膜、表面・界面
ホームページ
(16:10~16:30) 高分子のらせん構造を活かした機能性材料の開発
飯田 拡基講師(工学研究科物質制御工学専攻)

DNAやタンパク質などの生体高分子はらせん構造を形成し、生命維持に不可欠な高度な機能を発揮しています。私たちのグループでは、これら生体高分子に類似したらせん構造を有する高分子化合物を人工的に合成するとともに、得られたらせん高分子を用いて、既存の高分子の性能を凌ぐ新しい機能性材料を開発することを目指し研究を行っています。本講演では、その最新の成果について紹介します。
[キーワード]:らせん構造、高分子、機能性材料
ホームページ
B会場(豊田講堂3階)
梅原 徳次教授(工学研究科機械理工学専攻)

次世代トライボロジー材料として潤滑油不要で超低摩擦となる窒化炭素膜(CNx膜)を紹介します。また、DLC膜を含む硬質炭素膜における紫外線照射による低摩擦化技術を紹介します。さらに、マイクロ金型や高度小型機械部品のに適用するための基礎技術として、高密度プラズマを援用した直径1mm、長さ50 mmといった細管内面への新しいコーティング法を紹介します。
[キーワード]:自動車、航空機、医療機器、しゅう動材料、軸受、低摩擦、低付着
ホームページ
(12:00~12:20) これからのものづくりを支える切削加工技術を目指して
社本 英二教授(工学研究科機械理工学専攻)

当研究グループでは、従来にない加工法や機械要素、生産スケジュール手法等を創案し、従来技術では不可能であった超精密・微細・高能率加工等の実現に挑戦しています。それらのいくつかは産学協同研究を経て実用に至り、多くの製品製造に用いられています。本講演では、それらの新技術の中で、切削加工に関する技術に絞って概説致します。具体的には、(1)楕円振動切削加工法による高硬度材の超精密・微細加工、(2)切削加工におけるびびり振動の解析と抑制、(3)切りくずの制御・引張りによる絡み付き防止と高能率加工について概説します。
[キーワード]:生産技術、機械加工、切削、びびり、超精密、微細、切りくず
ホームページ
石原 一彰教授(工学研究科化学・生物工学専攻)

アミド、エステル、酸無水物などのカルボン酸誘導体は、各種有機材料のモノマーとしてのみならず、医薬品中間体、香料、化粧品、化成品などに広く使われています。また、官能基選択的有機合成のための水酸基、アミノ基、カルボキシル基等の保護基しても有用です。既に多くのカルボン酸誘導体合成法が開発されていますが、化学量論量以上の縮合剤を必要とする等、解決すべき課題は多い状況です。しかし、本来、カルボン酸からの触媒的脱水縮合反応によってカルボン酸誘導体を合成できれば、アトムエコノミーの観点から理想的と言えます。本研究室ではボロン酸やホウ酸にカルボン酸を活性化する働きがあることに着目し、カルボン酸の脱水縮合反応を促進するホウ素触媒の開発研究を行っています。本講演では最新の研究成果を織りまぜながら、その実用性・有用性に焦点をあて、最近の目覚ましい技術革新について紹介します。
[キーワード]:ホウ素、触媒、エステル、アミド、カルボン酸無水物
ホームページ
(13:30~13:50) エネルギー基盤材料としての耐熱金属材料
村田 純教教授(工学研究科マテリアル理工学専攻)

発電プラントや化学プラントをはじめとする各種プラントや熱機関は耐熱構造用金属材料により支えられ、それらの効率は耐熱金属材料の耐用温度に依存しています。金属材料の耐熱性はそのナノ・ミクロ組織形態と密接に関連していますが、そのミクロ組織はこれらの材料が使用される温度で時々刻々と変化します。したがって、耐熱金属材料を理解し、新たな材料を開発するには、そのミクロ組織変化の主要因を明らかにすることが重要です。この講演では、ニッケル基超合金や先進耐熱鋼におけるミクロ組織変化の本質を、実験とシミュレーションによりミ明らかにした例を紹介するとともに、今後の展望を述べます。
[キーワード]:ミクロ組織制御、耐熱金属材料、フェーズフィールドシミュレーション
ホームページ
(13:50~14:10) 金属およびセラミックス系複合材料・多孔質材料の構造制御による多機能化
小橋 眞准教授(工学研究科マテリアル理工学専攻)

金属やセラミックなどの材料中に気孔を導入することにより超低比重、断熱性能、衝撃吸収能力、流体透過性能、巨大表面積、集電性能など様々な機能を生み出すことができます。また、異種材料の接合界面では、界面につくられる凹凸構造により接合強度が向上することが、よく知られています。私たちの研究グループでは、このように材料内部あるいは表面におけるミクロな空間構造(かたち)を制御することにより新機能を生み出す研究を行っています。また、そのような空間構造を作るための様々なプロセス開発を進めています。講演では、私たちの研究室で開発した反応プリカーサ法による空間構造制御方法について紹介します。
[キーワード]:ポーラス材料、多孔質材料、複合材料、材料軽量化技術
(14:10~14:30) 利用開始目前! 先端分析の新拠点 中部シンクロトロン光施設でわかること
田渕 雅夫特任教授(シンクロトロン光研究センター)

名古屋大学シクロトロン光研究センターがバックアップし建設している中部シンクロトロン光センターが、今年度オープンします。
施設の概要を示し、その立上げ状況について報告するとともに、設置している各ビームラインの特徴とその利用分野を紹介します。
[キーワード]:放射光、材料、分析、半導体、X線
(14:50~15:10) 新しい超短パルス光源を用いた3次元光断層計測技術
西澤 典彦教授(工学研究科電子情報システム専攻)

本研究室では、新しい高機能な超短パルスファイバレーザー光源の開発と、それを用いた3次元光断層計測技術の研究などを行っています。光源、計測技術とも、医療から化学、生物、機械系と応用範囲の広い技術です、当日は我々のシーズと応用例をご紹介します。
[キーワード]:レーザー、医療、光ファイバ、超短パルス、非破壊検査
ホームページ
(15:10~15:30) ナノ解析は名大超高圧電子顕微鏡グループへ
春日部 進特任教授(エコトピア科学研究所ナノマテリアル科学研究部門)

名古屋大学超高圧電子顕微鏡施設では、世界最高水準の電子顕微鏡観察・分析技術を保有し、各研究機関、産業界などとの共用事業を推進し、技術課題の解決を支援しています。講演では、当施設の支援体制、利用申し込み方法および観察例を紹介いたします。電子顕微鏡操作技術に精通した専任技術陣および学内の各専門分野の研究陣(研究室)の解析サポート体制のもと、分析方法の選定、試料の作製、観察・解析・評価と一体となった支援体制で観察結果を提供いたします。故障解析、反応現象の解明、新物性の探索、高信頼性の確保など、皆様の技術開発の鍵となる材料評価手段として、本施設をぜひご活用ください。
[キーワード]:電子顕微鏡、構造解析、元素分析、ナノ材料
ホームページ
(15:30~15:50) アンケートデータの見える化
吉川 大弘准教授(工学研究科計算理工学専攻)

可視化によるアンケートデータ解析プラットフォーム(VDA: Visual Data Analyazer) ver.2を開発しましたので紹介します。予備調査による質問項目設計、結果の集計・多変量解析とテキストマインニング、回答者群の属性解析、自由記述欄解析などを全てVDA上で実施できるようにしました。類似質問・カウンター質問解析、まじめ度・関心度解析、インタラクティブグルーピング、アソシエーション分析、階層化キーワードグラフによるトピック解析など研究室オリジナルの解析手法、可視化手法をたくさん盛り込んでいます。
[キーワード]:アンケートデータ解析、多変量解析、テキストマイニング、アソシエーション分析
ホームページ
(15:50~16:10) 癌の迅速診断デバイスの開発
笠間 敏博研究員(工学研究科化学・生物工学専攻)

癌による死亡者数は、医療の進歩している現在においても、日本人の死因の第一位を占めています。その主な原因は、病変の早期発見の難しさにあります。我々は、癌に罹患すると血液や尿などの体液に漏出するタンパク質(癌マーカー)に着目し、これを高速、高感度、操作が容易でかつ低コストに検出・定量できる免疫診断デバイスを開発しました。このデバイスを利用して、これまでに極微量の前立腺特異抗原(前立腺がんマーカー)やC反応性蛋白(炎症マーカー)などの定量に成功しています。講演ではこの内容について発表します。
(16:10~16:30) 歯髄幹細胞由来成長因子を応用した新しい中枢神経治療
松原 弘記医員、井上 崇徳医員(医学系研究科細胞情報医学専攻/医学部附属病院歯科口腔外科)

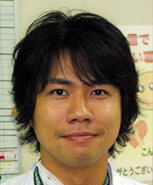
近年、幹細胞が分泌するサイトカイン等の様々な成長因子群の治療効果が注目されています。幹細胞由来成長因子のみを使用するのであれば、幹細胞移植で障壁となる問題(免疫拒絶、腫瘍化する危険性や倫理的問題など)はその大部分が解消できます。
当研究室ではこれまでヒト歯髄幹細胞に着目し、その高い中枢神経再生効果を報告してきました。本講演では、歯髄幹細胞より抽出した成長因子群の投与による難治性中枢神経疾患である脳梗塞および脊髄損傷疾患モデルでの劇的な治療効果と、治癒メカニズムについて報告します。本研究結果により、細胞移植を必要としない、新たな中枢神経疾患治療法確立の可能性が示唆されています。
[キーワード]:再生医療、再生医学、組織工学
※写真上は松原 弘記医員、下は井上 崇徳医員
(16:30~16:50) 見やすく疲れない3D立体映像をめざして
宮尾 克教授(情報科学研究科情報システム学専攻)

3D映像は眼が疲れるといわれてきました。その原因として、調節-輻輳矛盾説が上げられてきました。これは、3Dでは、調節のピントは画面に固定され、寄り目の焦点だけが、バーチャルな位置に移動します。この矛盾のことです。日米のガイドライン・解説書でおなじみの記述です。しかし、3D映像でも、水晶体調節はバーチャルな位置に移動することがわかりました。そこで、バーチャルな位置に調節のピントが合うのならば、映像がボケて見えるのではないか、という疑問が出てきました。また、眼疲労の真の原因はなにか、という疑問も上がっている。こうした新たな疑問に解答を与え、疲労の少ない自然な3Dを実現するための方向性をお話しします。
[キーワード]:3D、水晶体調節、両眼輻輳、眼疲労、3D映像酔い
ホームページ
共催/大学院医学系研究科、大学院環境学研究科、大学院情報科学研究科、大学院創薬科学研究科、エコトピア科学研究所、シンクロトロン光研究センター、グリーンモビリティ連携研究センター、減災連携研究センター
後援/経済産業省中部経済産業局、愛知県、名古屋市、一般社団法人 中部経済連合会、名古屋商工会議所、公益財団法人 中部科学技術センター、公益財団法人 科学技術交流財団、公益財団法人 名古屋産業振興公社、中部エレクトロニクス振興会、東海ベンチャービジネスドットコム、財団法人 ソフトピアジャパン、公益社団法人 計測自動制御学会 中部支部、独立行政法人 中小企業基盤整備機構中部本部 名古屋医工連携インキュベータ、名古屋大学協力会、中日新聞社、日刊工業新聞社、フジサンケイビジネスアイ
協賛/公益財団法人 名古屋産業科学研究所